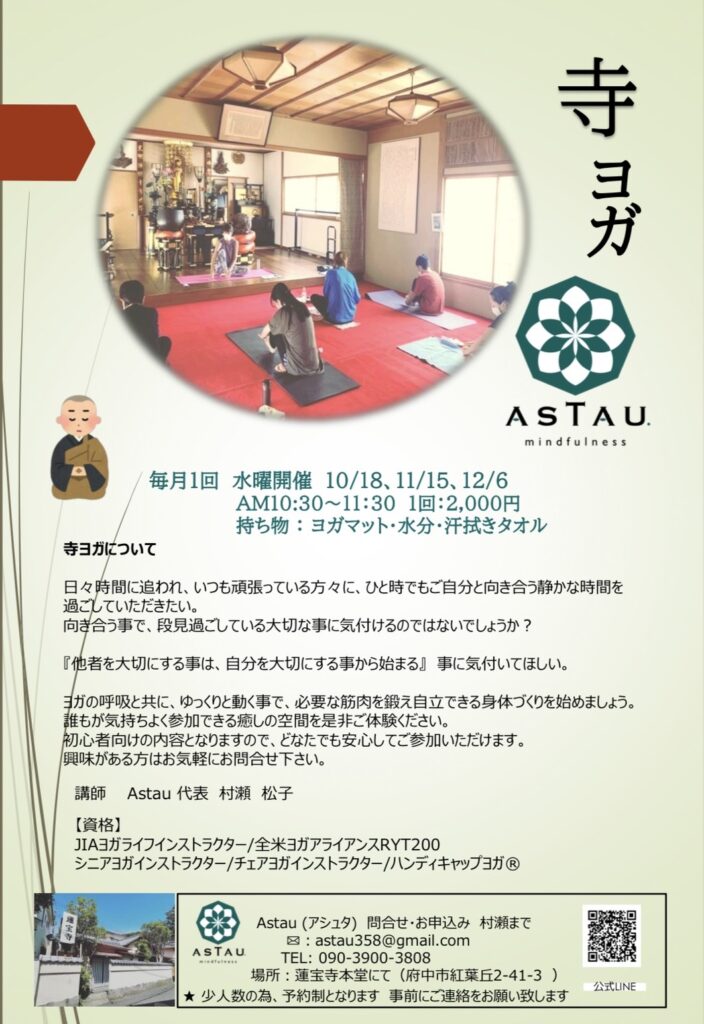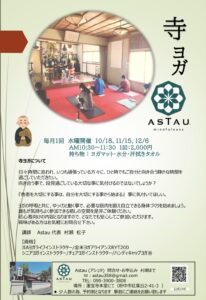7月7日に施餓鬼法要をおつとめし、36名のお参りをいただきました。
府中市では午後2時に最高気温36度という予報でしたので、朝から1階・2階のエアコンを全開にして、寺全体を冷やすように試みたものの、外気温とみなさんの熱気とで、結局かなりの暑さになってしまったのではと思います。
それでも、最後まで参列していただいたこと、誠にありがたいことと感謝申し上げます。
春のお彼岸では、法要前に口腔機能についての健康講話をしていただきましたが、今回はミニコンサートを初開催。シンガーソングライターの山口春奈さんに、ピアノとハープで弾き語りをしていただきました。
施餓鬼のご詠歌をピアノでアレンジしていただいたり、「七夕」や「ふるさと」といった唱歌、映画「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」、亡き人とのつながりや祈りをテーマにしたオリジナル作品など、1時間弱にわたるコンサート、優しさと透明感あふれる歌声にみなさん、心癒されるひと時でした。
秋の彼岸法要は9月23日(月・振替休日)を予定しています。
適度な栄養と休養でこの夏を乗り切りましょう!