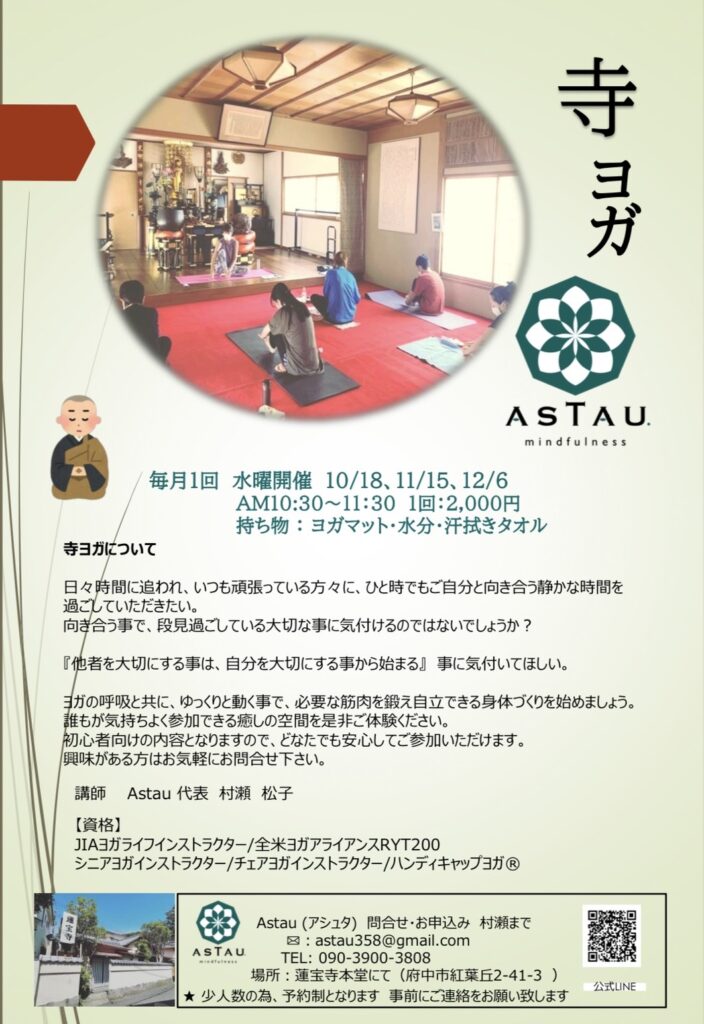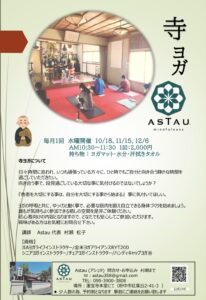寺報『信友』233号の巻頭「思わぬ効能」を転載いたします。
―――――
1月1日に発生した能登半島の地震・津波は、正月気分を一気に吹き飛ばしました。信友のみなさんのなかにも、能登に親戚や友人がいらっしゃる方もおられるでしょう。心よりお見舞いを申し上げます。
震災のニュースに触れると、どうしても2011年の東日本大震災を思い出してしまいます。テレビや携帯電話から地震のアラームが鳴るやいなや、瞬時にして、あの時に戻されるような感覚。みなさんもおありではないでしょうか。それだけ私たちの心に深い痛みとして残っているのでしょう。
当時は連日のように死者が何名、行方不明が何名といったニュースが流れ、テレビ画面には嘆き悲しむ被災者が映し出されていました。そして、被災者のほとんどは、近しい誰かを亡くした遺族でもありました。
大震災の発生から少し経った頃、ある女性のお話をうかがう機会がありました。その方は、若い頃にご両親を自死で失うという悲痛な経験をされ、今は同じような経験をされた人たちを支える活動をしています。
テレビもラジオも新聞も震災報道一色だった頃、どう過ごしていたのかという話になりました。地震・津波でたくさんの人が亡くなったという報道は、被災地から遠く離れた場所にいても、遺族には無関係ではなく、胸がかき乱されるもの。自分が家族を亡くした時の記憶がよみがえったり、蓋をしていた感情が爆発しそうになったり……。
「ニュースは一切見れませんでした。でも、テレビやラジオをつけないと、孤独に押しつぶされそうになる。被害はだいたい分かっているから、ニュースを見なくても、いろいろ考えてしまって、落ち込んでしまうし……。」
では、どうやって乗り切ったのかと聞くと、こんな答えが待っていました。
「通販チャンネルってあるでしょう。24時間、365日、生放送で通販をしているところ。あれをずっとつけていたんです。震災のニュースはやらないし、暗い社会と無縁の世界。生放送だから、なんとなく同じ時間を過ごしている気分で、孤独感も和らぎました。」
全く想定外の答えに、目からうろこ。苦しさのなかで、もがき、たどり着いた逃げ道が、通販チャンネルだったのです。
たしかに、よく見ていると、通販チャンネルの人たちは、いつも明るく、前向きなことしか言いません。「赤のMサイズ、売りきれました!」とライブ感が伝わり、今、同じ時間を生きているんだ、自分は一人ぼっちじゃないんだと思わせてくます。
それ以来、私も孤独を感じたり、気持ちが上向かなかったりしたとき、通販チャンネルをボーッと眺めます。どんな夜中でもいつも笑顔で、フライパンで肉を焼いたり、スカートを履いたり、楽しそうです。(何も買ったことはありませんが)
これって、実はとても大事なことなのです。自分の心を知り、ダメだと感じた時にはしっかり守るということ。震災報道に疲れてしまった時に限りません。寂しさやしんどさにおそわれたら、だまされたと思って、通販チャンネルをつけてみてくださいね。