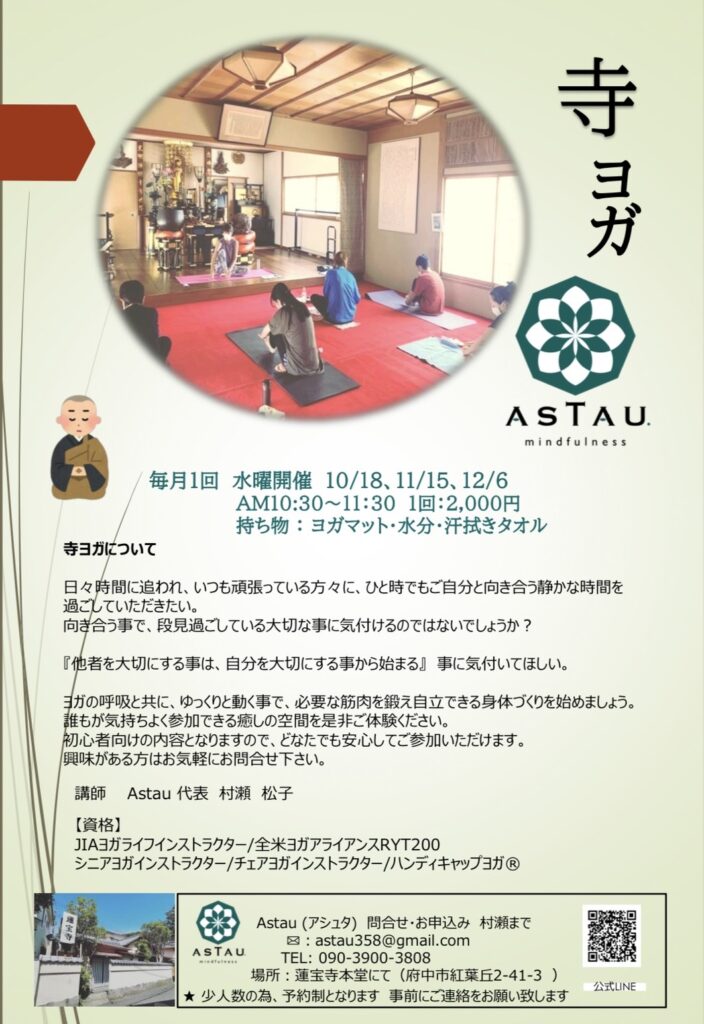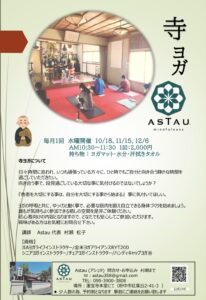寺報『信友』232号の巻頭「怨みをすててこそ」を転載いたします。
―――――
今年も残りわずかとなりました。
一昨年の年末の信友には、「世界全体では、楽より苦が多かったように感じます。来年は苦よりも楽が多い一年になりますように」と書き、昨年の年末には、「去年より今年の方が『楽より苦』が多かったのではないでしょうか。来年こそは、笑顔あふれる一年になりますように」と書いていました。
さて、今年一年を振り返るとどうでしょう?
コロナはある程度おさまり、日常が戻ってきました。虎党の私としては、阪神タイガースの優勝に心躍らせたのですが、社会全体、世界全体を見ると、やはり今年もなんだかどんよりとした一年だったように感じます。
特に戦争の報道は胸がふさがれますね。ロシア・ウクライナだけでなく、今年はイスラエルとパレスチナ(ハマス)との戦闘が起こりました。私自身、ここ数年で母の看取りや子どもの誕生を経験したばかりなので、病院で患者や新生児が犠牲になるニュースは胸が張り裂けるようです。
亡くなられた人だけでなく、懸命に看病していた家族、赤ちゃんをお腹の中で大事に大事に育ててきたお母さん……、みんな、どんな思いでいるのでしょう。もし私が同じ立場なら、狂ってしまった方がどんなに楽かと思うかもしれません。かたき討ちをせずにはいられないと銃を取るかもしれません。
そんなことを考えるとき、お釈迦様の言葉が浮かんできます。
実にこの世においては、
怨みに報いるに怨みを以てしたならば、
ついに怨みの息(や)むことがない。
怨みをすててこそ息む。
これは永遠の真理である。
(『ダンマ・パダ』より)
怨みへの報復は、さらに怨みを生み出し、そのサイクルは止まることはない。怨みを捨ててこそ、怨みの連鎖は終わるのだと説かれています。世界の紛争だけでなく、私たちの身の回りをみても、その通りだと思う言葉ですね。
お釈迦様がこの言葉を残して2500年が経っていますが、悲しいことに、世界中で怨みはやんでいません。人間は怨みを簡単には捨てられないのだということを分かったうえで、お釈迦様は諭されたのでしょう。やはり、私ももしそんな目にあったなら、怨みを捨てられるのかどうか、はなはだ自信がありません。
実は、浄土宗の開祖・法然上人は、幼少期に押領使(地方行政職)だった父親を敵対する豪族に殺害されています。父親は臨終の間際に、かたき討ちはせず仏門に入って父の菩提を弔うようにと我が子(法然上人)に言い残したと伝えられます。
法然上人が残した浄土の教えとは、この世は苦しみに満ちているけれど、阿弥陀様の極楽浄土は苦しみも怨みも悲しみも一切ない世界。どんなに弱い愚かな人間でも阿弥陀様に救われて、極楽浄土に往けるというもの。
法然上人の生い立ちを考えると、浄土宗の教えは、法然上人が抱えていた怨み、人間の弱さを直視し、血がにじむような修行の末に出会われた法然上人ご自身の救いだったのではないかと思えてきます。
もちろん、極楽浄土があるからこの世で怨みを捨てなくても良いというわけではありません。少しでもこの世界で怨みの連鎖が断ち切られますよう、私自身も自戒したいと思います。
来年こそは苦よりも楽が多くなりますよう、心から願います。